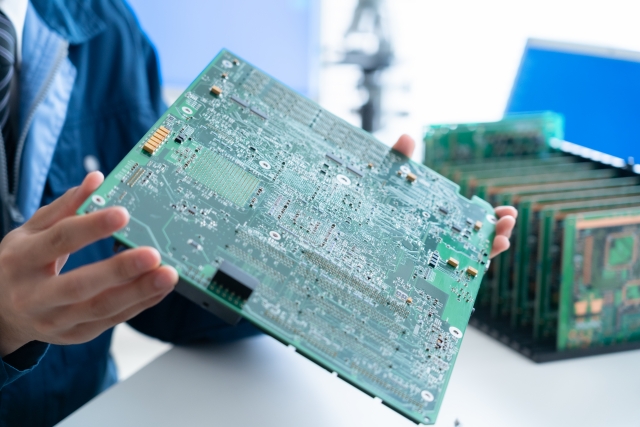
組み立て経験者が語る!「やりにくい基板」のリアル
今回は入社3年目のわたくし”セラミコ”がお届けします!
私は今では基板設計をしていますがシナノセイケンに入社する前は、
とある工場で組み立てのお仕事をしていました。
その製品は1台を組み上げるために20種類近くの大小さまざまな基板を
組み込む必要がありました。
それだけの種類があると中には作業がやりにくい基板もあります。
という事で今回は私が経験した組み立て作業がやりにくかった基板について、
その当時の内容と、今の目線で少しお話しようと思います。
組み立ての現場で感じたこと
当時の工場では、使用する基板自体は実装までされたものが納品されており、
あくまで『1つの部品』として組み込むのみでした。
ですので私自身、組み立ての知識はあれど、基板の知識はさっぱりでしたので、
製品の頭脳の役割がある事は知っていたものの、
「基板って賢いな~。」程度のペラペラの感想しか出てこないレベルでした。
当時、組み立て作業の際に基板へのコネクタが差し込みにくい場所がありました。
そのコネクタ周辺に背の高い電解コンデンサが実装されていたのです。
コネクタを真っ直ぐ差し込むのにちょっと邪魔な位置でしたので
接続不良も出やすく注意が必要なところでした。
基板サイズや条件、回路などの都合上、仕方なく電解コンデンサをその位置に
配置したのか、それとも特に気にせずその位置に配置したのかは
今となっては分かりません。
設計者の視点から考える「やりにくい」をなくすために
基板設計をしていますと、中にはどうしても部品配置が厳しい基板もあります。
一方組み立て作業者としては、不良の心配が無く作業しやすい基板に
越したことはありません。
基板設計をする上で、回路設計者に求められている機能や性能を満たし、
不具合の無い基板設計をする事はもちろん重要です。
それに加え、基板が完成した後の作業がしやすいように設計することも
非常に重要になってきます。
より良い設計を目指していくことが、最終的には製品全体の品質向上に
つながります。
私自身がそのような「作業がやりにくかった」という経験があるからこそ、
設計者として基板で作業をする方々の視点に立った設計を行うことで、
少しでも「作業しやすい」基板をつくるお力になれたら幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
